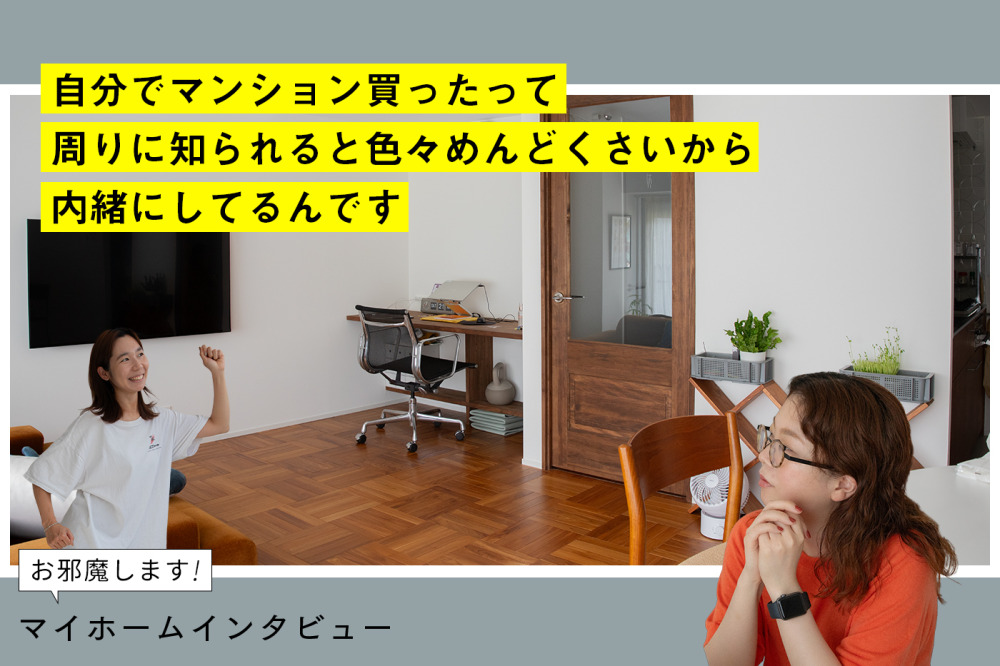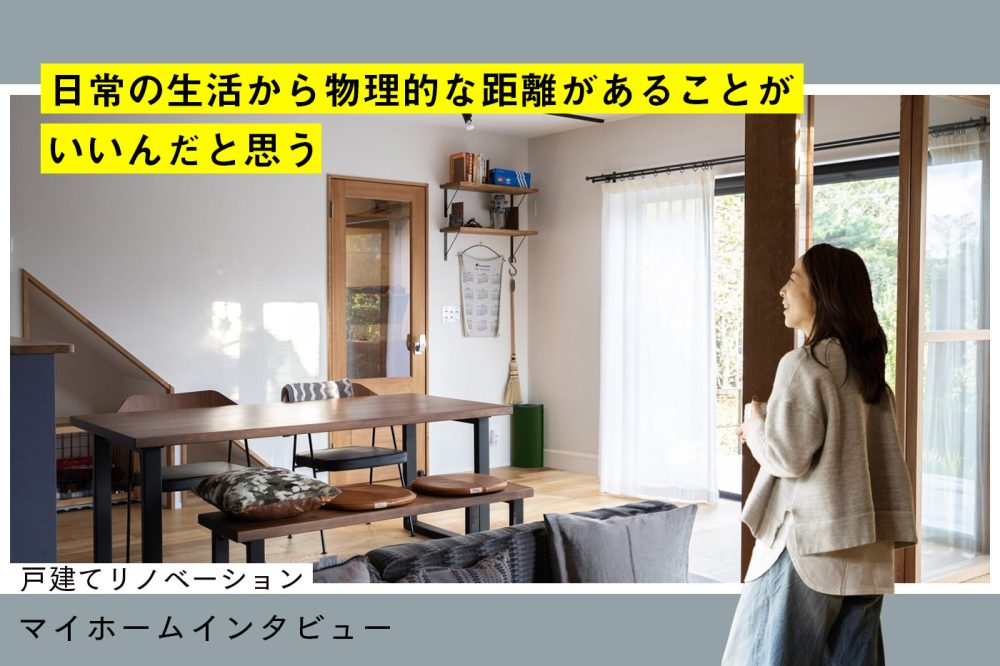古建具や障子をキーに、線と面を効果的に使う、宮田さんのリノベーション。今回届いた事例は、木をふんだんに使った直線的な空間に、潔く球体の照明を採用しています。
「ミルクガラス照明」は、名前の通りミルクのようなツヤのある白いガラスグローブの照明。水平と直線で描かれた空間に、ぽってりとしたフォルムがアクセントになっています。
天井は躯体をあえて露出させずに、ラワン合板を目透かし貼りに。建具の印象と合わさり、ノスタルジーを感じます。
写真右奥の建具にご注目。サッシが二重になっているのがわかりますね。実は、内側に古建具をつけているのです。
こちらの窓サッシには障子を。マンションでは共用部分とされる窓サッシを宮田さんが得意とする古建具使いで巧みに隠しました。マンションらしさが削ぎ落とされ、古民家のような窓辺に仕上がっています。
対面キッチンは、大谷石貼り!四方のほとんどを木に囲まれた空間のなかで、ゴツゴツした素材感や白とも違う大谷石らしい色味が映えています。
“キッチンは住宅の顔”と考えているという宮田さん。大胆に重厚感のある素材を取り入れたことで、物件の中で一際目をひく空間になりました。
格子状の造作棚が書類をピシッとまとめてくれる作業場でありながらも、ふと見上げると、ぽてっとした照明が照らしてくれる。
線と丸、固さとやわらかさのような対比する要素を各所に散りばめた空間は、住宅を兼ねた仕事場にぴったり。どこか懐かしく、でも背筋が伸びる感覚もあるような、唯一無二の空間事例でした。
宮田一彦アトリエ
古家の改修が大好物な鎌倉の設計事務所です。
現状残された要素を自分なりに解釈して住みやすい空間に再構築。 傷や汚れも「味」に思える空間が理想です。 懐古趣味ではないれけど、ベースである古家へ敬意を払う。そんな想いで設計しています。
紹介している商品
KB-KC017-12-G141
¥110,500
関連する事例記事
ここは、まちへの入り口。五城目の朝とゲストをつなぐ宿「市とコージ」
室町時代から続く朝市で知られる、秋田県・五城目町。その通りから一本入った小路に建つ「市とコージ」は、宿というより、ゲストを町へと誘う “入り口”のような場所。朝市で旬の野菜を買って、町をぶらぶら歩いて、戻ってきてキッチンでごはんをつくる。暮らすような滞在を楽しめる、町と旅人をつなぐ拠点です。
古さも新しさも、和も洋も、バラバラな素材を丁寧に重ねてつくりあげる築古戸建てリノベーション
今回ご紹介するのは、築50年の木造住宅をリノベーションした事例。
外見はごく一般的な2階建ての家に足を踏み入れると、古いものと新しいもの、合板と無垢材、和風と洋風など、色々な要素が混ざり合いながらも、違和感なく共存する空間が広がっていました。 一見バラバラに見える素材たちが、どうして心地よくまとまっているのか、それを紐解いていきます。
実家を引き継ぎ、“集まるリビング”を中心に再構築した、3世代6人の住まい
ご実家を引き継ぎ、両親を含めた3世代6人での暮らしに合わせてリノベーション。それぞれの生活リズムを大切にしつつ、みんなが集まれる場所をきちんとつくることを大事にしました。
ラフに見えて、気が利いてる。光と風を取り込む半屋外スペースがある、“倉庫っぽい”ワンルーム賃貸
1フロア1戸の賃貸物件で構成された、住宅地の中に建つ小さなビル。リノベーションによって生まれたのは、鉄骨やブレースが現しになったワンルーム。倉庫のような大らかな空間には、住む人の自由な使い方を受け止める工夫と、心地よく暮らすための気遣いが詰まっていました。
事例記事
toolboxの商品を採用いただいたお客様の事例を紹介しています。空間づくりの参考に。