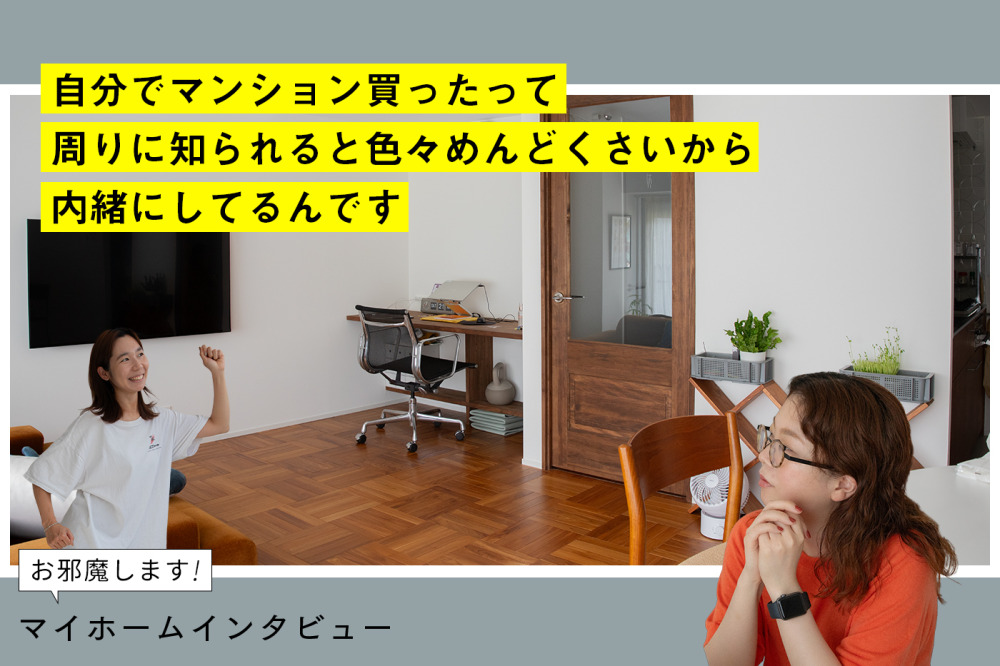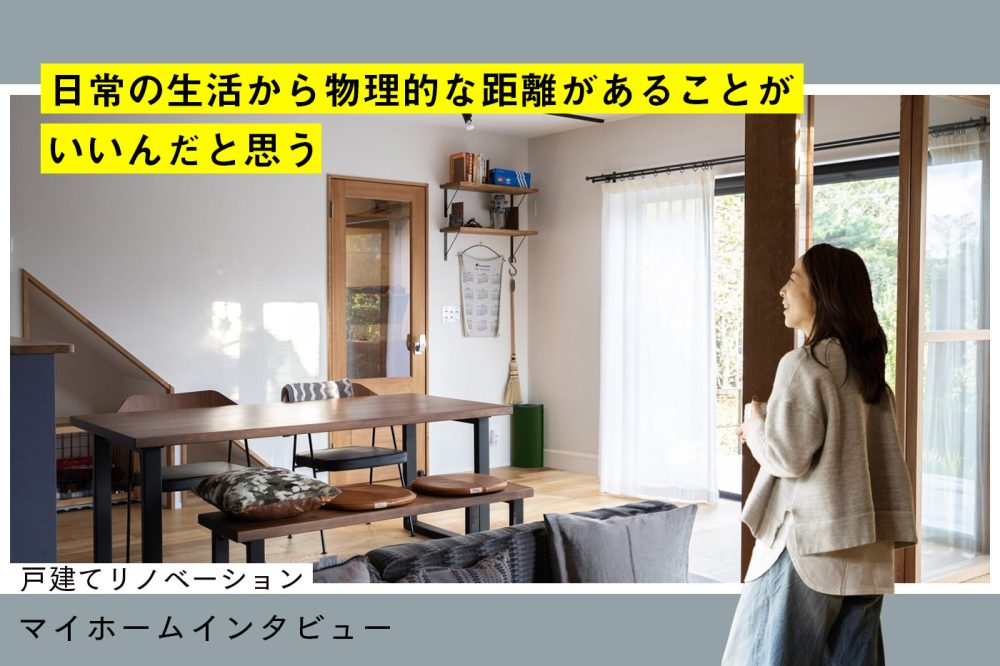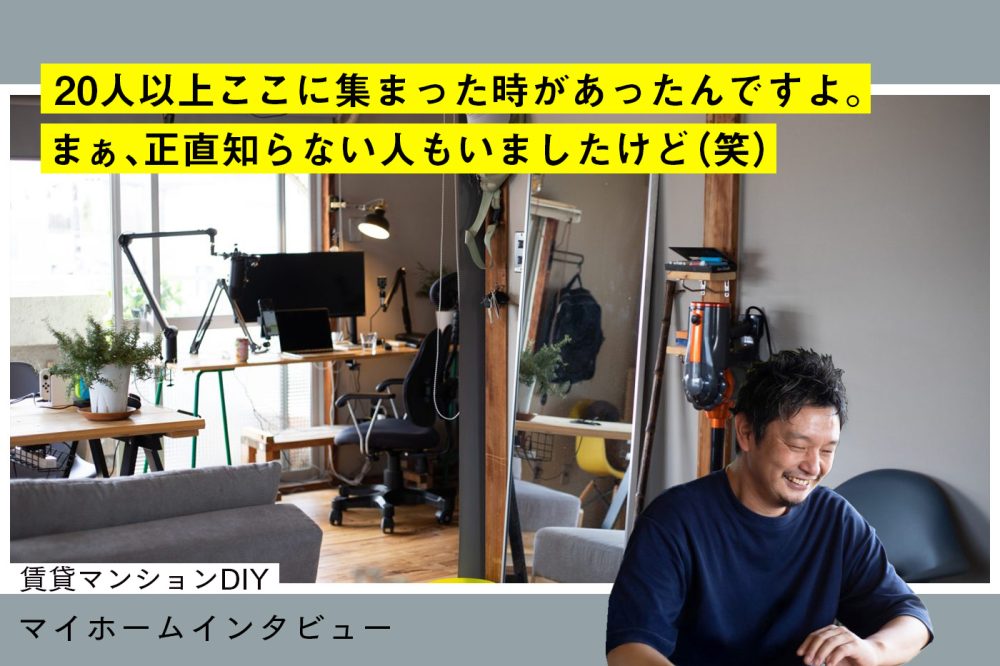このピラミッドのような家が建つのは、沖縄県にある住宅地。道路から奥に向かって下がっていく傾斜地で、まわりにはマンションや墓地があり、隣接する墓地は緑が生い茂っていて、静かな森のような雰囲気です。
沖縄では、お墓は「先祖が住む家」と考えられており、家のような形をしていて石積みやコンクリートで造られているのが特徴。親族が集まって先祖供養の宴をすることもある、沖縄の人たちにとって特別な場所です。
建物のかたちは、地面にどっしりと根を下ろすようなピラミッド型。傾斜地に配慮して、2本の太い基礎梁の上に建物を載せる構造になっています。まるでこの地に昔からあった“遺跡”のような、重厚な佇まいです。
「当初は沖縄らしく、開放的な家にしたいという想いもありましたが、この土地の環境を考えると、プライバシーへの配慮が不可欠。そこで早い段階から、窓を最小限にし、“外に対して大きな開口部を設けない家”という方向で設計を進めました。」と話すのは、この家の設計を手掛けた五十嵐理人さん。
沖縄では、昔は建材として使える木が少なく、台風対策の意味もあり、木造住宅は少なく、コンクリート造が一般的。壁は斜めに打設されており、外装・内装ともにコンクリート打放しにしています。構造そのものが空間の表情となり、シンプルで印象的な空間が生まれました。
ご夫婦からの唯一の要望は、「高低差のあるこの土地の特性を活かしてほしい」というもの。その思いに応えるため、建物は敷地の高低差に沿って3段構成とし、1段目に玄関とキッチンなどの水まわり、2段目にリビングと書斎、3段目に寝室などのプライベート空間を配置。土地の高低差をそのまま暮らしに取り込みました。
玄関から寝室までまっすぐ視線が抜ける空間は伸びやかで、外観に反してとても開放的。扉を開けると風が気持ちよく通り抜けます。
玄関を入ると、まず出迎えてくれるのがキッチン。ラワン材で造作された家具が、住まいとしての温かみのある雰囲気をつくっています。
水栓や金物には鉄やブラックのアイテムを使い、レンジフードも空間に合わせてブラックの『フラットレンジフード』を採用。各所に使う素材や色を一貫することで、ワンルーム状の住まいに洗練された印象をつくり出しています。
キッチンの先には、階段を下りてつながるリビングと書斎の空間が広がります。
コンクリートの段差にラワンの踏み台を組み合わせた階段は、リズム感が小気味よいですね。
昼間は、トップライトから差し込む自然光が、空間をやさしく包み込みます。壁の角度やトップライトの位置は、直射日光が入りすぎないように工夫をしているのだそう。天気の悪い日でもトップライトのおかげで室内は明るく照明いらずです。そして夜は、ところどころに設けられた壁付け照明が、空間に穏やかな灯りを添えてくれます。
トップライトの下にある、ラワンで造作された壁の向こうが書斎。たっぷりと設けられた造作収納にはワークカウンターも備わっており、仕事や読書など、さまざまな過ごし方ができます。足元に設置されたFIX窓からはやわらかな光が差し込み、開放感と静けさが同居する、心地よい居場所になっています。
そして、一番奥にあるのが寝室です。普段は開け放して過ごせるよう、引き戸はちょうどベッドが隠れるサイズで造作されています。寝室の上のスペースはキャットウォークとしても機能。愛猫も家の中を自由に行き来して、のびのび暮らしています。
外から見ると一見閉じた印象ですが、中に入ると広がるのは、光と風がたっぷりと入り、外へとゆるやかに開かれていく空間。このかたちは、沖縄の気候や雨風、周囲の環境に配慮して導き出されたものでもありました。
暑い夏の日も、嵐の日も、時が経って周囲の環境が変わっても。悠然とそこに在り続け、家族の穏やかな暮らしを長く慈しみ続ける住まいです。
撮影:神宮巨樹
IGArchitects/五十嵐 理人
1983年東京都生まれ。工学院大学大学院建築学専攻修了、~2014清水建設設計部、~2018年SUPPOSE DESIGN OFICEを経て、 2020年IGArchitects一級建築士事務所設立。人のふるまいを制限せず、変化や可能性を受け入れることのできる空間の強度を持った大らかな建築をつくりたいと思っています。
紹介している商品
関連する事例記事