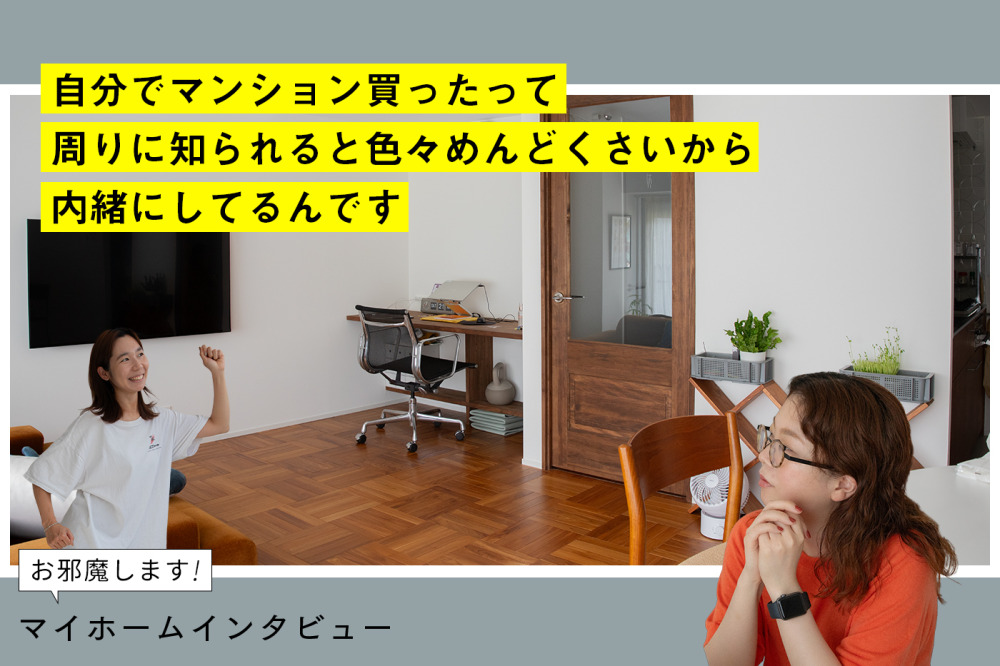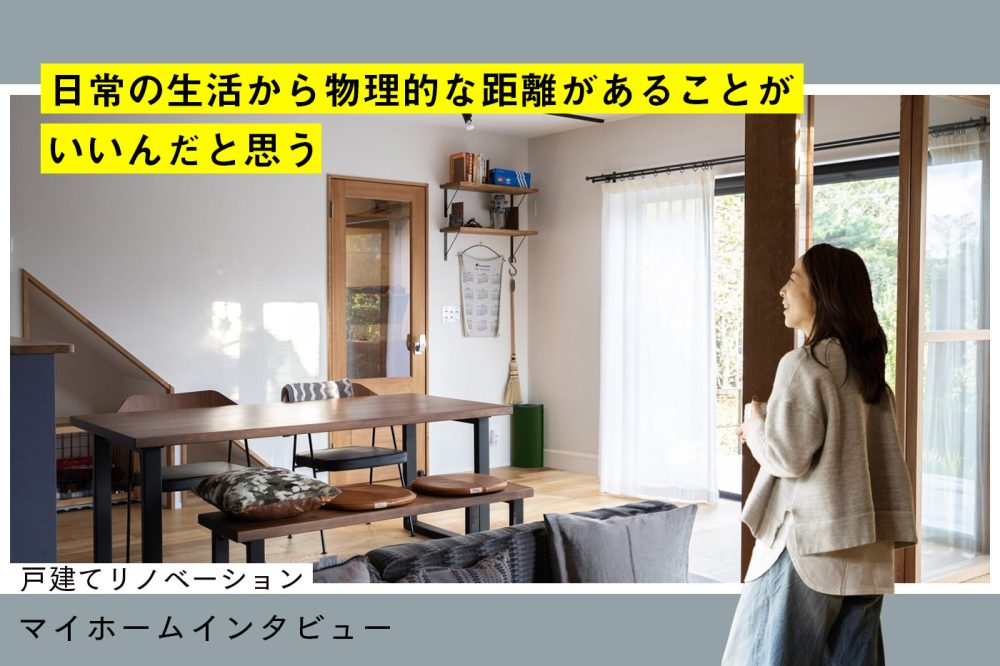東京・世田谷区の住宅街にある大きな窓がびっしりと並ぶ建物。ご近所さんの間で「あれは何?」と注目を集める存在です。それが、建築家の山野井靖さんが設計を手がけた自宅兼建築事務所。
横長の土地の敷地面積は63㎡。間口約13m、奥行き約3m。3階建てで、あえて個室を設けず、1階が事務所、2階リビング、ダイニングキッチン、お風呂等の水回り、3階(ロフト)が寝室兼子ども部屋になっています。
間口に対して奥行きはそこまで広くはありませんが、その開放感に入った瞬間から思わず「お〜〜」と声が漏れるほど。豊かに過ごすための工夫が随所に散りばめられていました。
街を取り込む
まず、印象的なのはやはり、南向きの窓たち。間口いっぱいに窓を設けました。
「『この家、窓多くない?』と通りすがりに言われているのを耳にしたこともあります(笑)」と山野井さん。
道路を挟んで向かい側には、50年以上前の大学キャンパス跡地があり、植栽が青々と生い茂っていました。大きな窓からは、その象徴的な赤レンガ塀や大きなヒマラヤスギが見え、季節になれば、桜や紅葉が加わって鮮やかになるんだそう。
奥の壁材には、窓から見える塀と同じ赤レンガを取り入れました。なんだか、外の風景とつながっているよう……。
視界を外に開くことで、間口の狭さを感じさせない空間になっています。
2階のキッチンの壁もレンガで統一。シェルフはインロー金物を使って、すっきりと見せています。
コンロ上にただずむ『フラットレンジフード』。レンジフードや冷蔵庫は天板と同じステンレスを選び、家電類の存在感を抑えました。
カーテンを壁にする
外と中をつなげている大きな窓たちには自作のカーテンがかかっています。全て閉め切っても、光を通したり揺れたりと軽やかな印象。これも、開放感をつくる要素になっているんだと思います。
「元々、ここまで多くの窓を作る予定はなかったんですが、妻の提案でカーテンを壁にすることにしました」
光や目線を遮るためだけではなく、壁として存在するカーテンは、アパレルで働くパートナーが自ら作ったもの。知見があるからこそ、ここまで大胆な窓の設計ができたのかもしれません。
光を取り入れる壁は、時間によって違う表情を見せます。夜でも、街灯や月の光を取り入れるので、真っ暗にはなりません。照明器具は必要最低限にし、外の光も取り入れながら過ごしているそうです。
床をテーブルにする
そして、お待たせしました。冒頭の写真をみた時から気になっていたであろう、もう一つの大きな特徴。各階の床に設けられたガラスのスリット。
長手方向にガラスのスリットが入ることで、奥行きがさらに強調され、広がりを感じます。
1階から3階まで、このガラスのスリット越しに各階がつながって見えるので、2.1mというそう高くはない天井高も、もう少しあるように感じます。
ガラススリットを支える根太は箱形にして構造にしているため、下から見ると規則性のある凹凸になっているのもポイント。
ガラス部分には強化ガラスを使用し、ヒビが入らないように木の部分と微妙に段差をつけています。大きな窓から入る光の量は、根太の高さで調整。夏は暑すぎず、冬は寒すぎないよう、太陽の傾きと根太の高さを緻密に計算しました。
2階から真下をのぞくと、1階のグリーンたちが、3階をのぞくと、人見知りをしてどこかに行ってしまった猫ちゃんと目が合いました。
室内窓などを使って隣室とのつながりを持たせる事例は多いですが、垂直方向でもつながりをつくれるとは!
上からや下からの目線が生活にプラスされることで、ふと猫の肉球が見えたり、家族が別の階で仕事を頑張っている姿が見えたり……そんな小さな幸せを見つけられる気がしました。
床のガラススリットはテーブルにも様変わり。「床に座って、ここ(ガラス部分)にグラスを置いて晩酌するのがいいんですよ。人を招いた時とかはいつも最後は床に座って話し込んでいますね」と山野井さん。
全てがフローリングや絨毯だと、どうしても床と認識してしまいますが、ガラススリットの部分があることで、そんな役割が生まれたんですね。
実は山野井さんは以前toolboxのグループ会社であるSPEACに所属していた建築家さん。「そういえば……」と、toolboxのスタッフの家に行ったときのことを教えてくれました。
「toolboxのスタッフの家にお邪魔して食事をいただいたことがあって、そのとき、住宅ってこんなに自由につくっていいんだ!って驚いたんです。この家は、自分は設計者であり施主でもあったので、設計者の立場を忘れて、自由にやってみようと思ったんですよ」
窓ガラスやカーテンを壁にしてもいいし、窓を床に設けてもいい。アパレル業界と建築業界で働く夫婦だからこそ成し得た自由な家でした。

株式会社山野井靖建築事務所
個人住宅、共同住宅、オフィス、店舗等の新築、リフォーム、リノベーションを行う設計事務所。
建物の実測、劣化調査、法適合調査から、建築、インテリアの設計・デザインまで横断的に行っています。
紹介している商品
関連する事例記事