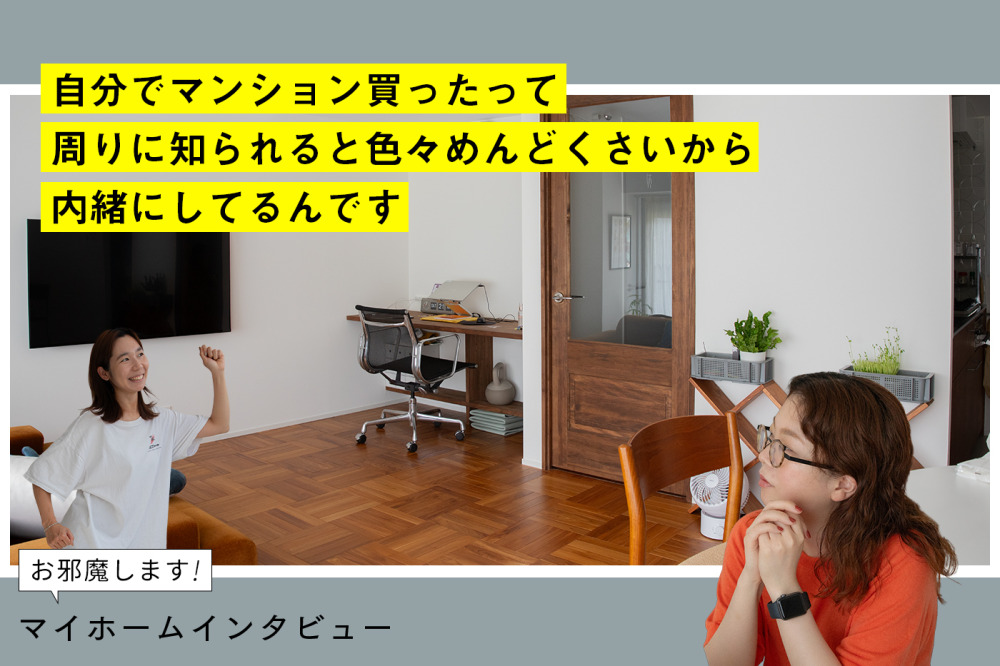施主である鶴岡さんからの要望はとてもユニークで、「鳥が集まる家にしたい。だから屋上に実のなる植物を植えたい」というものでした。
当時、鶴岡さんはこの鶴岡邸の裏手にあるマンションに住んでおり、そのベランダで鳥に餌をあげていたそうです。また、「そこは猫の通り道だから」など、目の前に広がる公園を自分の庭のように捉え、動植物との関わりを楽しんでいました。打ち合わせの際、その姿勢を目の当たりにした設計者の武田さんは、「なんとかこの要望を形にしたい」と強く感じたといいます。
植物を育てるには土が欠かせません。
しかし、通常の屋上緑化は、建物への負荷を考慮して浅い土を敷くのが一般的。樹木を育てるには深い土が必要です。
そこで武田さんが考えたのは、「屋根そのものを“植木鉢”のように捉える」という発想でした。起伏を設けることで、土の深い部分と浅い部分を生み出し、多様な植物が育つ環境を実現しました。
一方、敷地は住宅街にありながら、大きな公園に面しているため、強い風が吹き抜けます。家を守るためにまず検討したのは、丸いドーム型。そこから「公園側にはもっと開いてもいいのでは」と発想を広げた結果、特徴的なヴォールトの形状が生まれました。(※ヴォールトとは、屋根や天井をアーチ状に連ねた構造のこと)
起伏のある形状によって、雨水は自然に谷部に集まり、ドリップコーヒーのように孔を通してじんわりと地面へ落ちていく。建物自体が水の循環を生み出し、自然と共生する“器”となっています。
「自動設備に頼らず、雨水の循環だけで植物を育てたい」
そんな思いでつくったそうですが、実際には雨が降らず植物が弱ってしまうことも。そこで武田さん自ら水やりや剪定を手作業で行うように。
「手を入れると、次の日には植物が青々と生き返るんです。まるで子供のようで、愛着が湧いてきて。植物を知るいい機会にもなりました」と武田さん。
実は、現在「鶴岡邸」に住んでいるのは、武田さんご自身。設計途中で施主のお母様が亡くなり、施主自身も長年の夢だった京都へ移住。この家に住む理由がなくなった施主から武田さんに「この場所に住んでみませんか?」とまさかの打診があり、自邸兼事務所として使わせてもらうことになったのだそう。
今では、毎朝スタッフ全員で庭いじりをするのが日課に。
「これがなかなかよくて。身体を動かすのは気持ちがいいですし、将来独立したときにも植物の知識があれば提案に説得力が増しますよね」と武田さんは笑います。
そんな鶴岡邸のキッチンには、toolboxの『フラットレンジフード』が採用されています。
「建築は完成がゴールではなく、住み手が手を加えていくプロセスが面白い。toolboxのアイテムはシンプルで“余白”があるところがいい」と武田さん。
そう言って案内してくれたのは、写真右端に映るスイッチのある場所。『メタルスイッチプレート』が取り付けられ、配管はあえて剥き出しのままにしてあります。
「壁の中に配線を隠蔽してしまうと後から手を加えるのが大変。でもこうしておけば簡単に手を加えられる。建築もアイテムも、“変えていける余白”が大事だと思っています」と武田さんは言います。
その一例が、ヴォールト天井の谷部分。天井が低く手が届くため、アイボルトやワイヤーを取り付ければ、ハンモックやペンダントライト、プランターを自由に吊るすことができます。
「環境のための建築は、人が暮らす空間にとっても、新しい心地よさや合理性をもたらすのではないか」設計を進めながら、武田さんはそんな良い予感を抱いたそうです。
散歩の途中にこの家を見上げ、「中は一体どうなっているのだろう」と以前から気になっていた、練馬在住の私。今回、実際にお話を伺い、植物と共生する自然物のような佇まいと、そこに宿る設計思想が見事に重なっていることに深く納得しました。
「鶴岡邸」は、美しい住まいであると同時に、人、植物、鳥や昆虫など、多様な生き物が営む“生態系の場”にもなっています。建築が自然の一部として息づき、成長し続ける環境となる。時間の経過とともにどんなふうに変化を遂げていくのか、今後もウォッチしていきたい住まいです。
武田清明建築設計事務所
武田 清明(建築家)
1982年、神奈川県生まれ。2007年イーストロンドン大学大学院修士課程修了。2008年より隈研吾建築都市設計事務所に勤務。「自然と建築」をテーマに掲げて2019年に武田清明建築設計事務所を設立した。〈6つの小さな離れの家〉で「SDレビュー」鹿島賞、日本建築学会作品選集新人賞。〈鶴岡邸〉で東京建築士会「住宅建築賞」など受賞多数。住宅や共同住宅、福祉施設、ホテル、レストランなどの建築のデザインのみならず、プロダクトデザイン、そして植林の活動など、幅広く活動。
紹介している商品
関連する事例記事