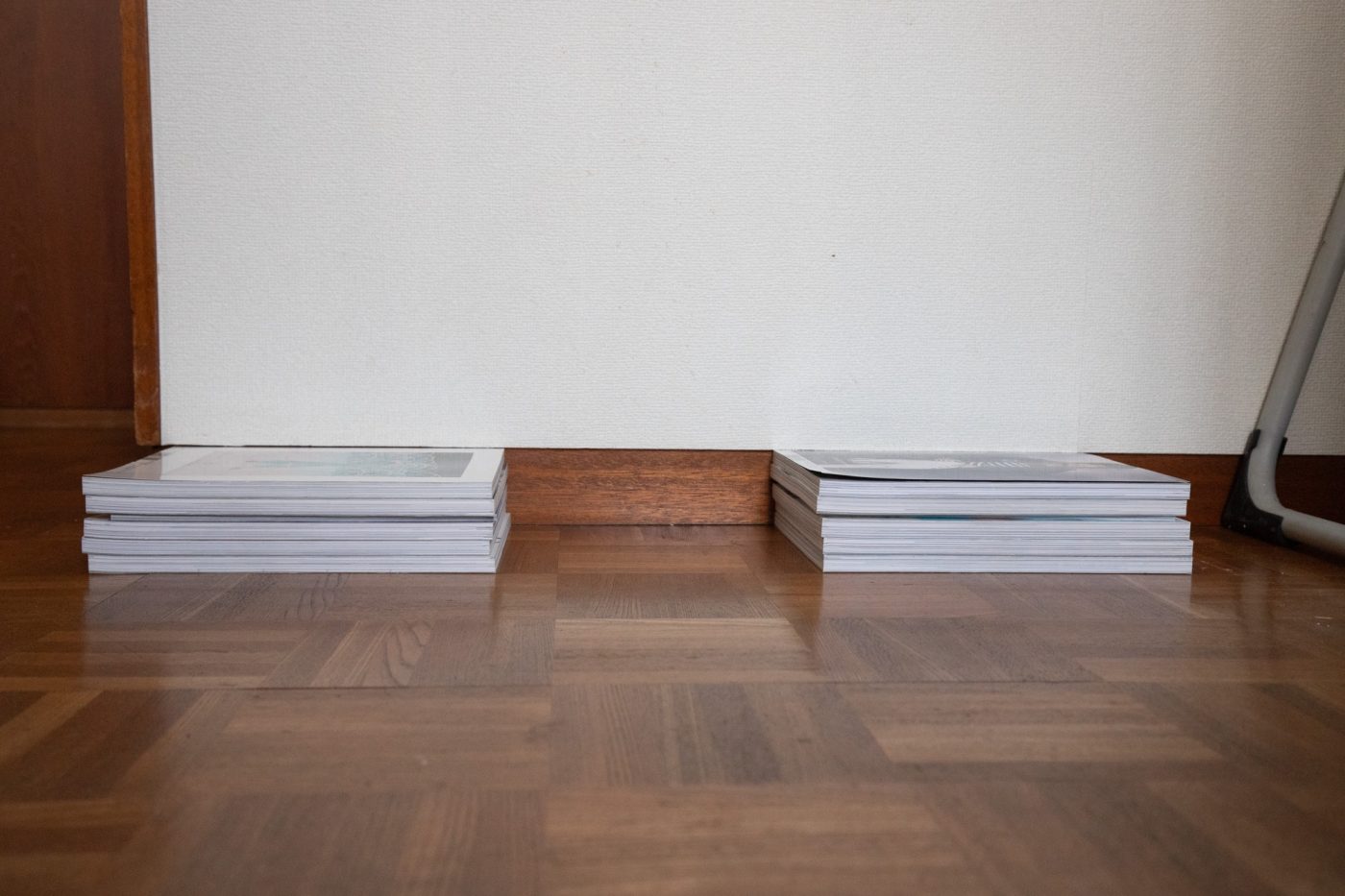DIYするのは、築46年の実家をDIYでアップデートしている、PRチームの三上。
現在の様子や私自身のことについてまとめた記事はこちらです。
今回はその実家DIYの第9弾。シリーズでは毎回、家の一部をDIYで変えていく様子をレポートしているのですが、今回は「玄関入ってすぐの壁」からお届けします。
施工するにあたって考えた事をもりもりと記載しています。何か参考になれば嬉しいです。
タイルを貼ったり襖を張り替えたり……過去にやってきたものは検索窓から「築古戸建の実家アップデート」で検索して「記事」項目から見ていただけます。
家の顔になる玄関入ってすぐの印象を変えたい!
今回手を加えてみたいな〜と思ったのは、玄関入ってすぐの正面にある壁。
元々この玄関に入ったときに見える景色は好きで気に入っていたのですが、月日が経ち壁の汚れが気になってくるように。また、飾るものを変える程度でしか変化がつくれていなかったので、何か変化が欲しいなと思うようになってきました。
玄関入った時の光景は、遊びにきてくれた方が最初に目にする場所で家の印象をかなり左右させるものだなとも思うので、より良くしたい。そのため、ここの壁に『ウッドウォールパネル』を貼って、アップデートさせることに決めました。
ウッドウォールパネルは、天然木の化粧パネル。1枚のサイズはW610×H2430mmでパネル状になっているので施工性が良く、DIYにも好相性な商品です。
バリエーションは「ニレ」と「ホワイトオーク」の2つ。今回は木目の幅が均一な「ホワイトオーク」の無塗装品を使用してみます!
「ウッドウォールパネル」を活用してどんな雰囲気にしたいか考えてみました。
商品コラムのメインに使われている事例や最近のイハウズさんの事例のような、木を印象的に用いたあたたかくて、レトロ感があるかっこいい(渋い)雰囲気をつくりたい。
もしくは、『ベンジャミンムーアペイント』などのカラー塗料で塗ってみるのもありだなと思ったり……。
でも、施工する我が家の玄関を改めて見渡すと、要素が結構多い。
この空間にカラーをさらに取り入れるよりも、シンプルに木目を活かす方が落ち着いていいのではと考え、今ある木の色味に合わせてオイル塗装することにしました。
使用するのは『ワトコオイル』。
「ワトコオイル」は木材表面に塗膜をつくらず、木の内部へとオイルが浸透するもの。木本来の木目や質感を保ちながら好みの色味に変化させることができる、植物油ベースの木部用オイルです。
ショールームでサンプルに試し塗りすることができるので、気になった色を試してみました。
試したのは「エボニー」「ドリフトウッド」「ダークウォルナット」の3色。
「エボニー」は渋くて色味自体はかなり好きですが、広い面に塗ったらちょっと暗いかも。「ダークウォルナット」は若干赤みを感じて、赤みがない方がいいかなと思ったり。「ドリフトウッド」は暗すぎず、でも赤みもなくちょうどいい色味のような気がする。
なんてことを持ち帰ってみたサンプルを当ててみて、もやもやと。
赤みがない方がいいのですが、改めて見てみると我が家の玄関に使われている木は意外と赤みがかっているのでは?と思い、そこに合わせた方がいいなと。
そこで、気に入った「ドリフトウッド」と「ダークウォルナット」を混ぜて塗ってみることにしました。
ちなみに第9回目にして初めてお伝えする情報ですが、家族も使うような共有の場所は、「何をやるか」「どんな色にするか」はいつも母と妄想して決めています。
ものづくりが好きな母なので、いつも盛り上がってあれやこれや事例を見ながら決めているのです。完成もいつも楽しみにしてくれています。
貼る壁面のサイズを確認して、商品を購入
続いては、施工面の採寸。壁は水平垂直に見えても、実は微妙に歪んでいることがあるので。 何箇所か測ってみます。
高いところは、写真のようにコンべックスを曲げて測ります。壁の上部に段差があったので、天井までではなく、その段差のないところまで貼りあげたいと思います。
施工したい部分を測ってみたら、2430mm × 1800mm。
「ウッドウォールパネル」の高さは、2430mm。施工したい部分になんとちょうどぴったり!ということで、高さはカットしないでそのまま施工できそうです。やった〜!
そして、横幅は1枚610mm。2枚はそのまま貼って、3枚目は少しカットして貼り付けることになりそうなので、購入するのは3枚。(私は新商品のサンプルをいただいたので、そちらをオフィスから自宅に持ち帰ります)
ウッドウォールパネルは1枚単位で購入可能。余分になるものが少ない状態で素材を購入することができるのは、DIYで施工する上ではかなり嬉しいポイントだなと思います。
裏面にボンドを塗って貼りつける
壁紙仕上げの壁に「ウッドウォールパネル」を貼りたい時は、壁紙を剥がしてから貼るのが一番丁寧なやり方。
ですが、我が家のクロスの状態をみたら剥がれもなく比較的いい状態だったことと。ボンドだけでなく、普段画鋲を刺したりフックをつけたりした時も問題なく、釘を刺して固定することができそうな壁だったので、クロスの上から貼ることにしました。
そう決断したのは、私のような素人が壁紙を剥がすことによってむしろ貼る面の状態が悪くなってしまうこともあるから。綺麗に剥がせたら問題はないのですが、クロスを綺麗に剥がすのもそれはそれで大変。剥がさなくてもいいのであれば、今回は剥がさなくてもいいのかなと判断しました。
もし釘を使用できない場合は、両面テープを活用してより強度を増すことをおすすめします。両面テープは一回壁に触れると微調整できないので、貼り付ける時はより慎重に!
パネルの裏面にボンドを塗るためにまずはボンドの準備から。
使用するボンドは「床職人」。フローリングを貼る時なんかも使用するウレタン樹脂系接着剤です。
一般的な木工用ボンドは木と木を接着するボンドで、木がボンドの水分を吸って反りやすくなるため、下地が木ではない場合は「ウレタン系ボンド」が適しているそう。今回は床職人で代用することにしています。
この時に気をつけたことは、ボンドを平たく塗ること。
「ウッドウォールパネル」は厚みが4mm。そこまで厚みがあるものではないので、ボンドの厚みが場所によって異なるとそれが完成形に影響することも。ボンドを塗ってない箇所があると浮きやすくもなります。
できるだけ全面均一に塗ったほうがピシッと決まるので、なるべく平たく均一に塗るように心がけました。
そして、今回はより密着性が高まるよう、塗ったボンドをクシ目をたててみることにしました。
また、パネルの端部が一番剥がれやすいので端は念入りにボンドをつけるように。でも、貼った時にはみ出ることはないように、より慎重にボンドを塗ることを心がけます。
ボンド塗り完了!
満遍なく塗るようにしたら「ウッドウォールパネル」1枚に対して、床職人(ボンド)1本を使い切りました。
ボンドが周辺につかないように注意して貼る場所に持っていきます。
今回は床にぴったりではなく、巾木より上の白い壁の部分に貼り付ける予定。
2400mmとなかなか長いのでまあまあ重い。そのまま貼り付けたとしても釘で固定するまでの間に下にずれそうなので、貼る位置の高さに合わせて雑誌を置いてみました。
養生する時は、雑誌がシートの下に来るように。
そして、その雑誌の上に載せるようにしてパネルを貼り付けます。
位置が確定できたら、ボンドが壁にしっかりくっつくように押し付けます。
壁に対して体重をかけるのは意外と難しいのですが、なるべく全体に体重をかけるような気持ちで押してみました。
釘で固定する
ボンドは硬化して固定されるまでに時間がかかるので、貼ったらすぐに釘を打って固定します。
使用する釘は「パネル釘」。「隠し釘」も使用できますが、平たい頭がある「パネル釘」の方が持力が強いのでおすすめです。
我が家のホームセンターにはパネル釘がなかったので、似たような形状だった引戸のレール用の釘で代用しました。
四隅とその中間地点など、20〜30cmピッチで釘を打っていきます。
最初は目立たないようにと思ってパネルの溝に打ってみたのですが、溝であるがゆえに最後まで打ち込むことができませんでした。(釘〆という道具を使うとうまくいくみたいです)
化粧パネルは本来は釘が目立たないように溝に打つものですが、試しに溝ではなく平なところに打ってみたら、想像よりも綺麗に埋め込まれて目立たない!その後は平らなところに打っていきました。
釘は斜めに打ち込むと抜けにくくなるんですが、今回の釘は頭が小さいから斜めにやろうとするとかなり打ちにくい。ということで斜めの気持ちは持ちつつも、やりやすいようにほぼ垂直に打ち込んでみることにしました。
また、真っ平らに見える壁でも微妙に凹凸があったりするので、貼ったパネルが浮き上がってくる可能性も。パネルの端部だけでなく中央部、横方向も20-30cmのピッチで釘を打っていきます。
今回は貼ったそばから壁の歪みで浮いてくるところがあったので、そこは少し多めに釘を打ってみました。
釘の頭が平らになっているので、最後まで打ち込むと綺麗に溶け込む。この綺麗さに感動して、打ち込むのが結構楽しかったです。
見る角度によってきらりと光るので全く目立たないということではないかもしれないですが、私はこのきらり感が好き。
真鍮という素材を選んだのはよかったのかもしれないな〜と思いました。
印をつけてカット!薄い板をカットするのにはコツがいる
高さがぴったりなことはそうないかと思うので貼り付ける前にカットする流れが一般的かもしれないですが、私は高さがぴったりだったので、まずはカットが必要ないものを先に貼ってみました。
それは、全体の横幅を測って2枚貼った分の横幅を計算で引くと、貼り付けのときに少しのずれなどがあった時にうまくいかないのではと考え、実寸で残りの幅を測った方が確実だと考えたためです。
ということで2枚貼り終えた残りの幅を測ります。
すると、なんと下の方、上の方、真ん中で幅が違う……。一番大きいところだと10mmほど差があって綺麗に合わせていくのは難しいなと。
頑張ろうと思えばできると思いますが、そんなに見える場所じゃないしそこまで細かく頑張らなくてもいいかという考えも働きました。面倒くさくなって楽しめなくなるのも嫌ですしね。
ということで、一番目につくであろう目線の高さのところに幅がぴったり収まるように。そこに合わせてまっすぐカットしていきます。
長さを改めて測ったらカットするパネルに墨付けを。
会社から差し金を持って帰って来るのを忘れてしまったので、家にあった三角定規とふつうの定規を活用して、垂直に長さを測って印をつけます。
私は書くのに失敗したら嫌だなと思って裏面に印をつけてしまったのですが、仕上げ面を表にカットした方がよかったみたいです。それはカットした時のバリがでにくいのと、寸法誤差が少ないから。(手鋸は特に刃が斜めになったりもするので)
次に、その印を線で繋ぎます。マジックは修正ができないので、鉛筆で書く方がいいですが、私は目が悪いこともあり鉛筆だとよく見えなかったのでマッキーで書いてしまいました。これは裏面だからできたことだとは思います。
のこぎりでカットするのには、パネルを上に浮かす必要があります。
作業台があると本当はいいのですが、私は家にあった机と椅子を活用することにしました。
机は面積が広めなので、膝をついてしっかりとパネルを抑えることができたので即席の割にはかなりよかったです。
環境が整ったら、のこぎりでカット!
最初に浅く刃を引いて、ノコギリがずれないようにガイドとなる溝をつくります。
それから、線の上に沿って切り進めていきます。
厚さ4mmと薄いパネルなので、カットに力は入りません。ですが、長くて薄くて軽いのでカットの際に安定しなくて、少し切りにくい。
本来ノコギリは引いて切るものなのですが、下に押す方に力を入れるようにしてカットしてみるとうまく進んでいきました。
もうすぐ切り終わるというところで、切り落とす側をしっかり押さえていないと、重力や勢いで折れて断面がギザギザになってしまうことがあるので、切り落とす側を誰かに抑えてもらえると良いです。
DIYを重ねてきたことでカットの技術もアップしてきた模様。線に沿ってまっすぐ切ることができました!
カット後は断面をやすりで整えます。
使用するのは基本の道具工具の『サンディングペーパー』。ロール状になったやすりシートをペーパーホルダーにセットしているもので、やすり紙よりもかなり施工性が良くて好きな道具の一つです。
カットが完了し、壁に当てはめてみると、狙ったところはぴったり!いい感じなので、先ほどと同様ボンドと釘で貼り付けていきます。
ボンドを塗るのも3枚目にもなると上達しました。
なんでもやっていくうちにコツをつかんだり、どうやったらやりやすいのかポイントがつかめて来ます。その過程を体感できるのもDIYの楽しさだな〜と最近思います。
ちなみに端の隙間はこんな感じ。
塗装後に撮影したものにはなるのですが、壁の角になる部分で正面からみることもそんなにないのでよく見ないと隙間は気になりません。若干塗料が壁についている方が気になりますね……。塗装する時に隙間を目立たなくするために塗ってしまえと思っていたのですが、むしろ壁にはつかないように慎重にやるべきだったなとミニ反省です。
「ワトコオイル」で好きな色に塗る
「ウッドウォールパネル」の無塗装品は、好みの加減に着色して仕上げられるのが魅力。
貼り終えたら乾いたタオルで表面を拭き取って、最後に塗装をして仕上げていきます。
塗るのは1章でも紹介した「ワトコオイル」。悩みに悩んで決めた色を混ぜ合わせて塗っていきます。
今回選択したのは「ドリフトウッド」と「ダークウォルナット」ですが、若干赤みが強い方がいいかなと思い、「ダークウォルナット」が気持ち多めになるように容器に移します。そこまで厳密ではなくていいかと思い、持った感じの感覚で。
「ワトコオイル」は好きな色に調色できるのがかなり魅力的。オイル系なのでドロドロしておらず、混ぜ合わせるのも楽です。
混ぜたらカットした端材に試し塗りして、OK!だったら壁に貼ったものに塗っていきます。
塗るのはハケで。その後にウエスで拭き取るという工程です。
この時意識したのは上から下に流れるように塗ってみること。一枚分の横幅を一気に塗るのではなく、少し狭めに移動が必要ない幅で、上の方を塗ったら続くように下にも塗料を伸ばしていきます。
塗料は床に垂れるので養生をしっかりすることをお忘れなく!
そんなこんなで一度塗りが終わったら、染み込んでいない溜まった塗料などを、全体に馴染ませるようにウエスで拭き取りしていきます。
拭ってみるとかなり印象が変わりました。ムラになっていないか心配したのですが、綺麗に均一に染み込んでくれていたようです。途中で塗料が溜まっている箇所を整えたりしたのが功を奏した気がします。
1回でも十分仕上がりはよかったのですが、よく見える場所なので、なるべく綺麗に仕上げたいと、2度塗りも行うことに。
先ほどと同じように塗って、ウエスで拭います。
そしてまたまた外はかなり暗くなってしまいましたが、完成!
艶やかで上品な印象に。シックでかっこいい!理想通りの出来栄えです。
隙間になる壁も塗料で少し塗ってしまえと思って塗ってみたら、オイルだったので壁紙のぼこぼこからはみ出て茶色の塗料が壁にただついてしまった……みたいな状態になってしまいました。
上の方なので見ようと思わなければ見えないので、一旦はそのままでやっぱり気になるなと思ったら白く塗装しようと思います。
完成!
朝になり撮り直してみたのがこちら。玄関入ってすぐの印象がガラッと変わりました。
一番悩んだ色味もいい感じ。周りの木たちとあっている気がします。一晩経って色が少し落ち着いたように感じて、2度塗りしてよかったなと思いました。
そして今回使用した「ウッドウォールパネル」のパネルの木目の出方も綺麗。主張は激しすぎず、でも木なんだということがしっかりわかる。この感じが好きだなと思いました。
ここにはお気に入りの絵を飾りたいです。
高さ2400mm以上あって元々開放感のある玄関でしたが、このパネルが追加されたことで視線がより上に伸びるように。
天井いっぱいまで貼らなかったのも圧迫感を感じない抜けになってくれてよかったなと思います。