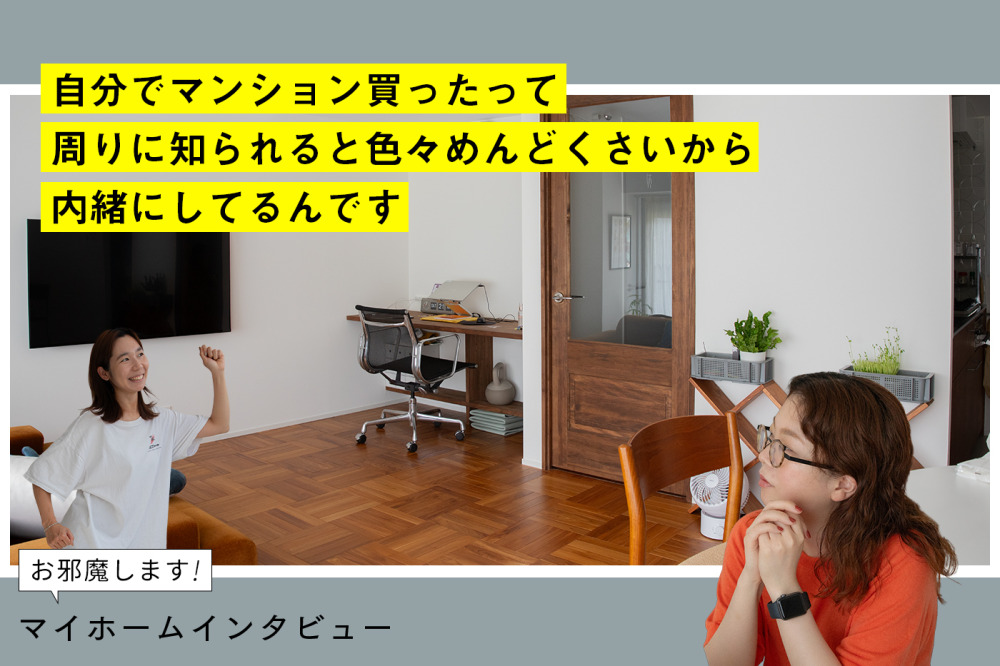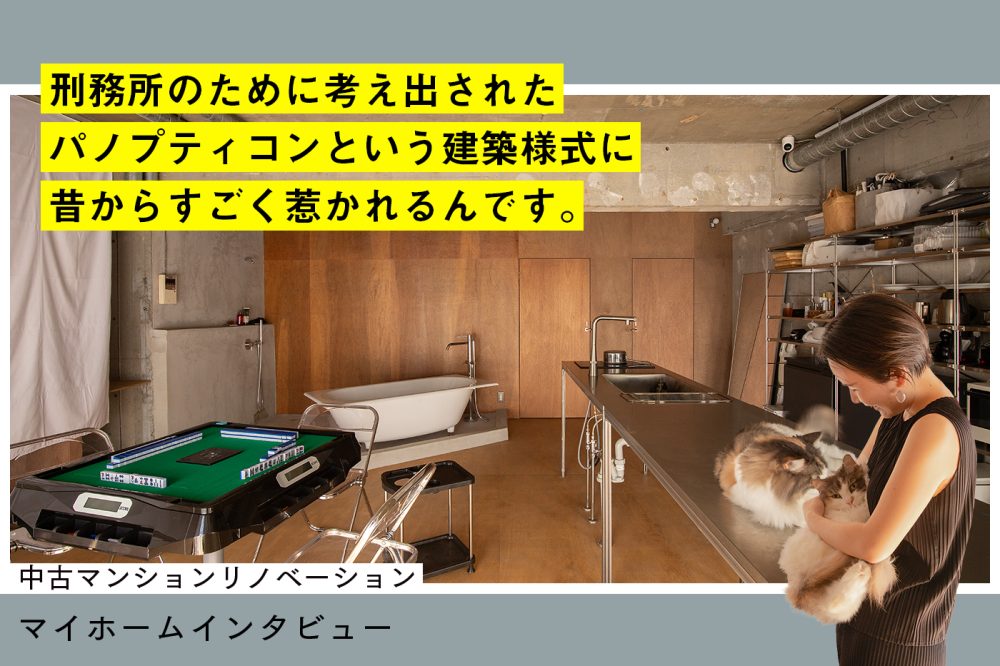隣接する鉄道の高架化工事のための用地買収の残地である、9坪弱のくさび形の敷地に建てられた、とても小さな住宅。
分譲前の土地に30年以上住まわれてきたお施主様の「この場所に住み続けたい」という強い思いから、残された9坪に満たない敷地に、こちらの小さな新居が建てられることになりました。
建物の外観がこちら。条例により外壁の後退を求められた北側は、その分バルコニーを区画いっぱいに延ばして設置しています。
このお家の特徴は、なんといっても建物の真ん中を貫く螺旋階段。
常に、階段の先の空間を感じることができるよう、階段は蹴込み板を無くした抜けのある構造に。また、室内に柱や壁を設けなくて済むよう、螺旋階段自体が構造となって建物を支えるつくりになっています。
「構造的に成立させながら、いかに開放的な空間にできるか。その検討は難しく同時に楽しいものでした」設計者である鈴木さんは、笑いながらそう語ってくれました。
「踏み板をなるべく広く取ることで、空間と階段との境を曖昧にして馴染ませたかったんです」
階段との境をより曖昧にするため、各フロアの床仕上げを階段まで伸張。リビングに伸びた踏み板が途中からソファ化していたり、階段がいつの間にか収納や玄関といった別の機能を兼ねる空間になっていたり。
空間と階段という区別を超えて、小さな空間が現れたり消えたりする、高さを変えながら連続するひと続きのワンルームのような一体感を感じさせる空間に仕上がっています。
また、フロアごとに個性を持たせるため、玄関はモルタル、リビングはカーペット、キッチンはPタイル、書斎はフローリング、クローゼットはスクールパーケット、ロフトはコルクといった具合に、フロアごとに床の素材が切り替わっているのもとってもユニーク。
約2.5畳と極端に小さなリビングスペース。にも関わらず、窮屈さをまったく感じさせません。それは、螺旋階段を通して、部屋の反対側に視線が抜けることで、床面積以上の広さを感じられるから。
小さな空間に籠る感覚がありながら、同時に、広いワンルームの一部にいる感覚を味わえる不思議。そのことについて鈴木さんは、「『小さな広大さ』を実現しようと試みたんです」そう、設計に込めた思いを説明してくださいました。
こちらは、約4畳のキッチンダイニング。
家具のような雰囲気に仕立てるため、キッチンは木で造作し、素朴な質感が特長の『古窯70角タイル』ミッドナイトブルーを組み合わせています。レンジフードは、「なるべく存在感がないものを」という考えから『フラットレンジフード』を採用いただきました。
そして、もう一つ。忘れてはいけないユニークなアイデアが、このお家のカーテンに潜んでいます。
極力空間を圧迫しないようにと、カーテンレールはダブルでなくシングルのものを採用。ただ、日々生活をおくる上では、完全に目隠しをしたい時もあれば、適度に視線を遮りながら光を取り込みたい時もあります。
そんな用途の使い分けを、シングルのカーテンレール上で叶えるというアイデアがこちら。
わかりますでしょうか?ガーゼカーテンと普通のカーテンを縫い合わせて一枚のカーテンに仕立てているんです。
中央の切り替え箇所にタッセルを設け、左右にかけ分けることで、2種類のカーテンを使い分けるという目から鱗のアイデア。こちらは、テキスタイルデザイナーの庄司はるかさんと一緒に考案したものだそうです。
クローゼット用にと計画されたフロアの入り口にも、必要な時に目隠しができるよう、間仕切り用のカーテンが設けられていました。
物理的に制限された窮屈な条件を、軽やかに広げてみせるアイデアの数々。暮らしを楽しむワクワクが詰まった、素敵なお住まいの事例でした。
(写真提供:西川公朗)
鈴木岳彦建築設計事務所
1987年埼玉県生まれの鈴木岳彦が、2019年に設立した設計事務所。東京 杉並にあるリノベーションしたマンションの一室を拠点に活動中です。
プロジェクトの種類や予算、大小に関わらず、ぜひお気軽にご相談ください。いつもそこにしか生まれ得ない空間、新しい心地よさを目指して、設計提案を行なっています。
紹介している商品
関連する事例記事