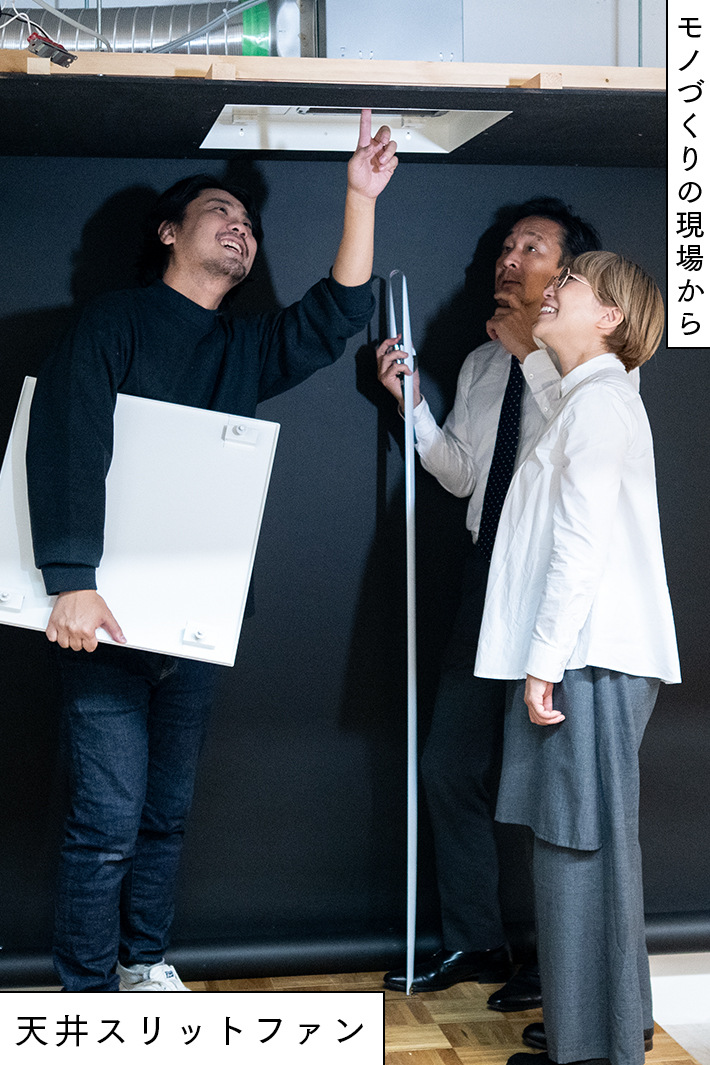『木の手摺』をつくっているのは家具職人の瀬尾洋介(せおようすけ)さん。手摺って家具?なんて思うかもしれませんが「手摺は家具に近い存在。」そう職人さんは話します。
家具を極めた職人だからこそつくり出せた、思わず触れたくなるような手摺。その手摺が生まれる過程を知るべく、製作現場を見せてもらいました。
ちなみに、瀬尾さんは、toolboxのサイトができたての頃に知り合い、今となってはtoolboxメンバーの一人といっても過言ではないくらい苦楽を共にしている仲です。
探し求めていた理想の手摺
手摺本体だけでなく、それを支えるブラケットも同じく無垢の木で作られている「木の手摺」。
無垢ならではの重厚感があり、木ならではの温かみと手触りの良さを併せ持った一品。
toolboxが関わったあるプロジェクトをきっかけに生まれたものなのですが、その出来栄えの良さから自然な流れで商品化に至りました。
探しても意外と見つからなかった、私たちが理想としていた手摺はまさにこの手摺だったんです。
ラフな材料に驚き
下の写真の右側3本が「木の手摺」の材料。
この状態を見ると随分ラフな印象ですよね。完成形の手摺の滑らかさが想像つきません。
ここから切り出し、滑らかにするためのやすりがけや面取りを行い、塗料を塗って仕上げていくんだそうです。
焦がさないテクニック
焦がさないって何を?って思いましたよね。
長い材料をカットするときはテーブルソーという工具を使ってカットするのですが、この手摺で使っているような比較的硬い木材をカットするときは、カッターと木材との間で摩擦が生まれ、木材が焦げてしまうことがあるんだそう。
一気にカットしようとすると摩擦が増えるので、瀬尾さんはできる限り焦がさないよう、同じ場所を3回に分けてカットしていました。
3回に分けても、下の写真のように少し焦げてしまうこともありますが、これくらいであれば想定内。
もともと焦げること前提に数mm大きめに切り出しているため、その後薄ーくスライスすることできれいさっぱりに焦げた部分はなくなります!
どうせ焦げるなら一気に1回でカットしたって同じじゃない?と思うかもしれませんが、1回でカットしてしまうともっと深いところまで焦げてしまうので、薄くスライスするくらいでは焦げが消えないのだそう。
3回に分けてカットするのは一見、手間に思えるかもしれませんが、材料を無駄にしないためには、とても大事な工程なのです。
丁寧に丁寧に角をとる
手触りの良い手摺をつくるため、トリマーという機械を使いスルスルと角を取っていきます。
トリマーは、最初に調整さえ終えれば、あとは角を取りたい箇所に添えて動かしていけば面取りができるという優れもの。
瀬尾さんは木材の状態を確認しながら丁寧に丁寧に面取りをして行きました。
考え抜かれた四角のブラケット
瀬尾さんが一番こだわったというのはブラケット。
手摺と同じ材でつくられているので、手摺本体との相性はもちろん、収まりも良いです。
パイプをL字に曲げたようなブラケットが多く出回る中では珍しい四角の形状は、見た目の良さを追求しただけでなく、手摺本体をがっしり支えられるようにと考えられたデザインなのです。
「木の手摺」は、制作だけでなくデザインも瀬尾さんによるもの。どちらもできる瀬尾さんだからこそ、美しさと機能性を兼ね備えたブラケットをつくることができたのではないでしょうか。
写真は長い角材から、ブラケット用にL型に加工された状態。この状態からコロコロとカットしていくのですが、その光景は金太郎飴をつくっているようで、見ていて楽しかったです。
小さくカットするところまで終えたら、ここからは地道な作業。
一つ一つビス穴の位置を印付けして、ドリルで穴あけ。片側から一気に貫通させてしまうと曲がってしまう危険もあるので、必ず両面からドリルを通して穴が曲がらないようにするんだとか。
この作業中、「地道だろー。」なんてぼやいてるわりには楽しそうに笑う瀬尾さんが印象的でした。
塗装前の最終仕上げは、完成形の滑らかな触り心地をつくり上げる重要な工程で、やすりがけです。
サンダーという電動工具を使えば早いのですが、細かな部分や、木の状態を確認しながら力の加減が行いやすいようにと瀬尾さんはあえて手作業で行います。
1本の手摺に対して何枚も消費するサンドペーパー。一体どのくらいでやすりがけが終わるのかを聞いてみたら「感覚」なんだとか。
自分の記憶にある滑らかさまで、ひたすらやすり続けるのです。
やすり終わった手摺を指でなででみると、さらりとした気持ちの良い触り心地がしました。
効率ばかりを求めない
瀬尾さんの作業を見ていて、瀬尾さんは作業効率を良くして早くモノを仕上げるということよりも、どれだけ「愛を注いでモノをつくれるか。」ということを大事にしているように思いました。
というのも、電動工具を使えばすぐに終わるような作業も手で行い、常に自分の手の感覚を頼りにモノづくりをされていたからです。
やすりにしても電動サンダーではなく紙やすりで行い、穴開けもボール盤という工具を使えば全てに印を付けなくても開けることができるのに、一つ一つ電動ドリルを使って穴を開けていました。
温かみのある製品を生み出すためには、手間ひまを掛けてモノづくりに向き合うことなのかもしれません。
「責任あるモノづくり」へのこだわり
普段は笑顔しか見せない瀬尾さんですが、作業が始まれば一変。スイッチが入ったと表現するのが一番ぴったりでしょうか?“クッ”と力の入った真剣な表情で、作業を進めて行きます。
「最初から最後まで責任持ったモノづくりがしたい。」
この言葉に込められた思いを反芻しながら、瀬尾さんのつくり出した「木の手摺」に触れ、改めてモノづくりの尊さを感じました。
製作の様子は動画でもご覧いただけます。
瀬尾商店:瀬尾洋介(せおようすけ)
関連記事
瀬尾商店
toolboxの初期から活動を共にしてくれている造作家具屋さん。
家具が専門でありながら、リフォーム・リノベーションなど何でもオールマイティにこなしてくれる頼れる存在。
戸越では「瀬尾商店」という名の雑貨も買えるオーダー家具店を営んでいます。